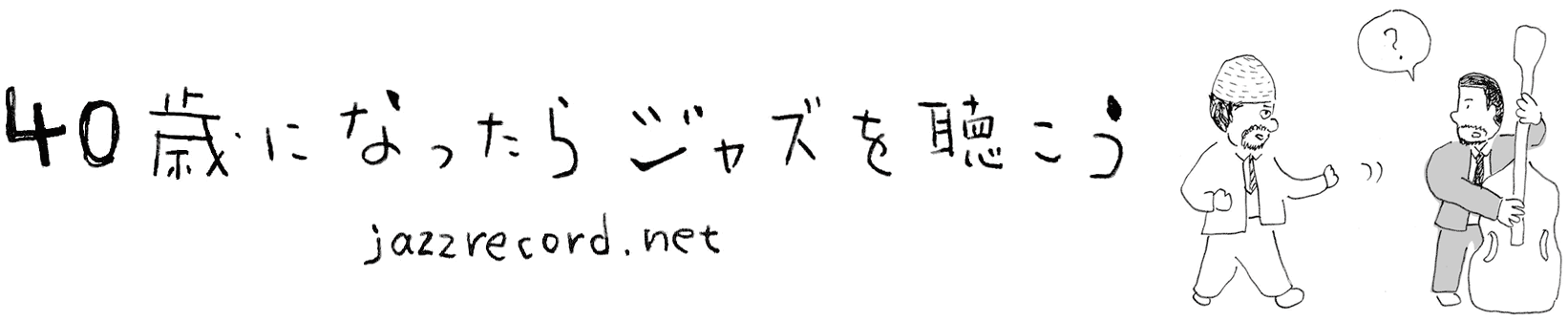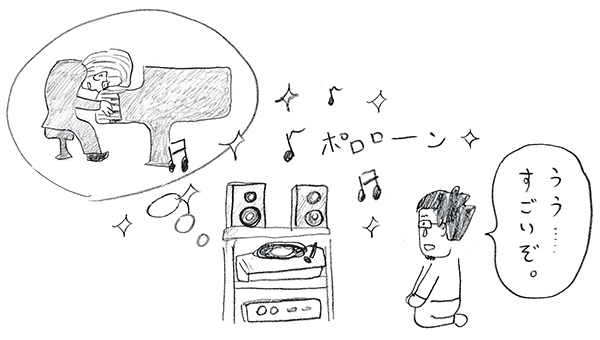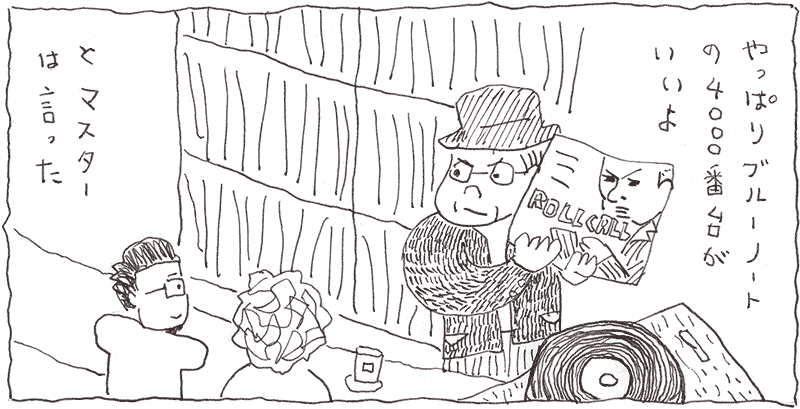小説家になる前はジャズバーを経営していて、いまでも膨大な数のジャズレコードを所有している村上春樹さん。彼の作品にはよくジャズが登場します。
ぼくは村上春樹さんの大ファンで、ジャズに興味を持ったのも、たぶん村上作品からの影響があると思います。そこで、村上作品に登場する「ジャズ」に関する記述を、ひとつひとつ拾ってみました。
とはいえ、じっくりと再読する余裕はなく、ささーっとページをめくりながらのピックアップ作業ですので、見落としている記述があるかもしれません。
また、短編も含めると膨大な数になるので、ここでは長編のみ紹介しています。
目次
風の歌を聴け
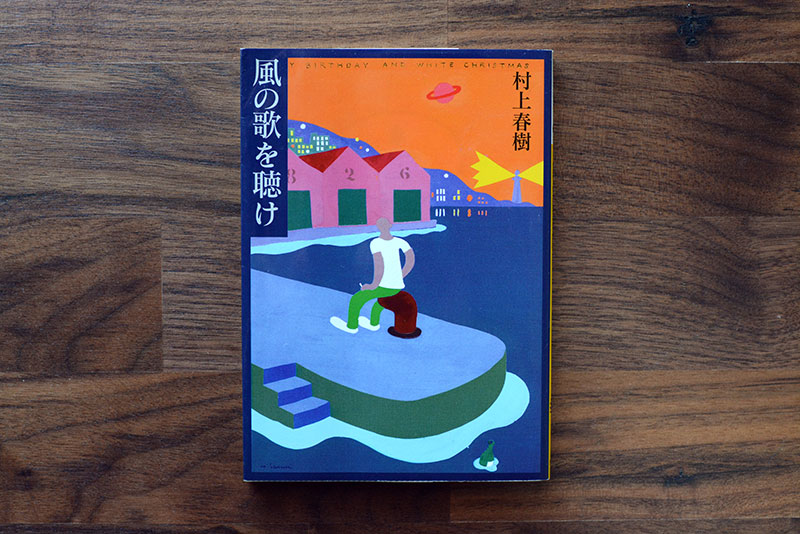
「他には?」「ギャル・イン・キャリコの入ったマイルス・デイビス。」今度は少し余分に時間がかかったが、彼女はやはりレコードを抱えて戻ってきた。
P65 ~ 小指の無い女の子とレコード店で再開した時の会話
僕たちは食後のコーヒーを飲み、狭い台所に並んで食器を洗ってからテーブルに戻ると、煙草に火を点けてM・J・Qのレコードを聴いた。
P91 ~ 小指の無い女の子の部屋
村上春樹さんのデビュー作。読み返すと、初々しいというか、今よりもずいぶんとキザな印象を受けてしまいます。
ジャズの登場シーンはたったの2つだけ。マイルス・デイビスのギャル・イン・キャリコの入ったレコードとは「Musings of Miles」ですね。マイルスの珍しいワンホーン・アルバムです。
こういうマイナーなレコードをあえて出してくるあたりが、やっぱりキザというか、若かったんだなあという感じがします。
1973年のピンボール

カセット・テープで古いスタン・ゲッツを聴きながら昼まで働いた。スタン・ゲッツ、アル・ヘイグ、ジミー・レイニー、テディ・コティック、タイニー・カーン、最高のバンドだ。「ジャンピング・ウィズ・シンフォニー・シッド」のゲッツのソロをテープにあわせて全部口笛で吹いてしまうと気分はずっと良くなった。
P73 ~ 翻訳の仕事をしながら
僕は窓を閉め、カセット・テープでチャーリー・パーカーの「ジャスト・フレンズ」を聴きながら、「渡り鳥はいつ眠る?」という項を訳し始めた。
P75 ~ 翻訳の仕事をしながら
仕事は峠を越し、僕はカセット・テープでビックス・バイダーベックやウディ・ハーマン、バニー・ベルガンといった古いジャズを聴き、煙草を吸いながらのんびりと仕事を続け、一時間おきにウィスキーを飲み、クッキーを食べた。
P131 ~ 仕事が暇な時期のすごしかた
僕は腰を下ろしたまま「ジャンピング・ウィズ・シンフォニイ・シッド」のはじめの四小節を口笛で吹いてみた。スタン・ゲッツとヘッド・シェイキング・アンド・フット・タッピング・リズム・セクション・・・。口笛は素晴らしく綺麗に鳴り響いた。僕は少し気を良くして次の四小節を吹いた。そしてまた四小節。
P151 ~ 探していたピンボールマシンが眠る倉庫
ジャズの登場シーンはデビュー作よりもすこし増えました。村上さんの大好きなスタン・ゲッツの曲(アット・ストーリーヴィルに収録)が登場します。
この小説で最も印象にのこる音楽シーンは、双子の女の子がこっそりビートルズの「ラバーソウル」を買っていたくだりかな。それを喜ばず不機嫌になる主人公はダメなやつです。
羊をめぐる冒険

200枚ばかりのレコードはどれも古く盤面は傷だらけだったが、少くとも無価値ではなかった。音楽は思想ほど風化しない。僕は真空管アンプのパワー・スイッチを入れ、でたらめにレコードを選んで針を置いてみた。ナット・キング・コールが「国境の南」を唄っていた。部屋の空気が1950年代に逆戻りしてしまったような感じだった。
下巻 P135 ~ 死後の鼠が待っていた山小屋
僕は納戸から古いギターをひっぱりだして苦労して調弦し、古い曲を弾いてみた。ベニー・グッドマンの「エアメイル・スペシャル」を聴きながら練習しているうちに昼になったので、もう固くなってしまった自家製パンに厚く切ったハムをはさみ、缶ビールを飲んだ。
下巻 P181 ~ 死後の鼠が待っていた山小屋
「戦争について何か聞いたかい?」と羊男が訊ねた。ベニー・グッドマン・オーケストラが「エアメイル・スペシャル」を演奏しはじめた。チャーリー・クリスチャンが長いソロを取った。彼はクリーム色のソフト帽をかぶっていた。それが僕の覚えている最後のイメージだった。
下巻 P211 ~ 死後の鼠が待っていた山小屋
この作品、ジャズはほとんど出てきません。上巻ではなんと1回も出てきません。
この小説は、村上さんが専業作家として書いたはじめての作品です。ジャズ喫茶「ピーター・キャット」をたたんだこの時期、ジャズからちょっと距離を置きたかったのかもしれません。
ジャズシーンは少ないけど、ぼくはこの作品が大好きです。耳に力を宿した女性、右翼の片腕、いるかホテルの支配人、羊博士、羊男、登場人物は魅力的で、話も抜群におもしろい。
「もうすぐ電話がかかってくるわよ」からはじまる村上ワールド。
世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド

「あなたアルト・サックス吹ける?」と彼女が私に訪ねた。「吹けない」と私は言った。「チャーリー・パーカーのレコード持ってる?」「持ってると思うけど、今はとても探せる状態じゃないし、それにステレオの装置も壊されちゃったから、いずれにせよ聴けないよ」「何か楽器はできる?」「何もできない」と私は言った。
上巻 P303 ~ ピンクのスーツを着た太った娘との会話
それで私はあきらめて、自分がウィスキーを飲んでいるところを頭の中に想像してみることにした。清潔で静かなバーと、ナッツの入ったボウルと、低い音で流れるMJQの「ヴァンドーム」、そしてダブルのオン・ザ・ロックだ。カウンターの上にグラスを置いて、しばらく手をつけずにじっとそれを眺める。ウィスキーというのは最初はじっと眺めるべきものなのだ。そして眺めるのに飽きたら飲むのだ。綺麗な女の子と同じだ。
下巻 P52 ~ やみくろの巣の暗闇の中での想像
それから私はレコード店に行って、カセット・テープを何本か買った。ジョニー・マティスのベスト・セレクションとツビン・メータの指揮するシェーンベルクの「浄夜」とケニー・バレルの「ストーミー・サンデイ」とデューク・エリントンの「ポピュラー・エリントン」とトレヴァー ・ピノックの「ブランデンブルク・コンチェルト」と「ライク・ア・ローリング・ストーン」の入ったボブ・ディランのテープという雑多な組み合わせだったが、カリーナ1800GT・ツインカムターボの中でいったいどんな音楽が聴きたくなるものなのか自分でも見当がつかないのだから仕方ない。
下巻 P242 ~ レンタカーを借りる前にレコード店で購入したカセット・テープ
「新しいものは読まないの?」「サマセット・モームならときどき読むね」「サマセット・モームを新しい作家だなんていう人今どきあまりいないわよ」と彼女はワインのグラスを傾けながら言った。「ジューク・ボックスにベニー・グッドマンのレコードが入ってないのと同じよ」
下巻 P267 ~ 図書館の彼女とレストランでの会話
私が適当に選んだテープにはジャッキー・マクリーンとかマイルス・デイヴィスとかウィントン・ケリーとか、その手の音楽が入っていた。私はピッツァが焼けるまで、「バッグズ・クルーヴ」とか」「飾りのついた四輪馬車」とかを聴きながら一人でウィスキーを飲んだ。彼女は自分のためにワインを開けた。
「古いジャズは好き?」と彼女が訊いた。「高校の頃はジャズ喫茶でこんなのばかり聴いてたな」と私は言った。下巻 P275 ~ 図書館の彼女の家で
次の曲はウディー・ハーマンの「アーリー・オータム」だった。
下巻 P301 ~ 図書館の彼女の家で
デューク・エリントンの音楽もよく晴れた十月の朝にぴたりとあっていた。もっともデューク・エリントンの音楽なら大みそかの南極基地にだってぴたりとあうかもしれない。
「デュー・ナッシン・ティル・ユー・ヒア・フロム・ミー」のユニークなローレンス・ブラウンのトロンボーン・ソロにあわせて口笛を吹きながら車を運転した。それからジョニー・ホッジスが「ソフィスティケーティッド・レディ」のソロをとった。下巻 P323 ~ 最後の午後、車を運転しながら
村上作品の中でも特に人気の高い作品。ぼくも好きです。何度も読み返すうちにちょっとずつ輝きを失っていきましたが、はじめて読んだ時はとてもワクワクしました。
上巻では全然ジャズが出てきませんが、下巻の後半で堰を切ったように出てきます。
レンタカー店の女性がボブ・ディランの声について「まるで小さな子が窓に立って雨ふりをじっと見つめているような声なんです」と語るシーンが、とても印象的です。ジャズではないけど。
それにしても、図書館勤務の彼女の家でジャズを聴くシーンがありますが、20代の女性がカセット・テープにジャッキー・マクリーンだのマイルス・デイヴィスだのを入れないですよね、普通。
ちなみにぼくが思い描く「やみくろ」の姿は、キン肉マンのアトランティスです。
ノルウェイの森
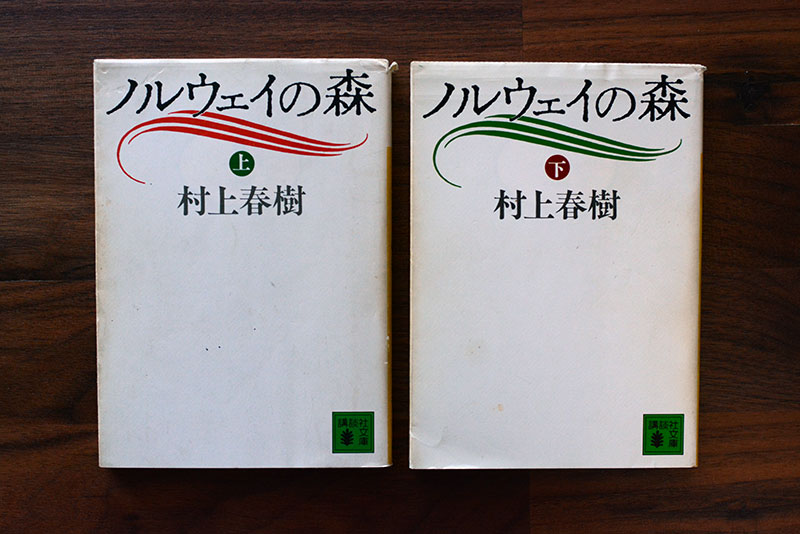
レコードは全部で六枚くらいしかなく、サイクルの最初は「サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド」で、最後はビル・エヴァンスの「ワルツ・フォー・デビー」だった。
上巻 P73 ~ 直子の二十歳の誕生日、彼女のアパート
部屋の壁には氷山の写真がまだしばらく貼ってあったが、やがて僕はそれをはがして、かわりにジム・モリソンとマイルス・デイヴィスの写真を貼った。それで部屋は少し僕らしくなった。
上巻 P92 ~ 突撃隊がいなくなった部屋
そしてドライヤーで髪を乾かしながら、本棚に並んでいたビル・エヴァンスのレコードをとりだしてかけたが、しばらくしてから、それが直子の誕生日に彼女の部屋で僕が何度かかけたのと同じレコードであることに気づいた。
月の光がとても明るかったので僕は部屋の灯りを消し、ソファーに寝転んでビル・エヴァンスのピアノを聴いた。上巻 P197 ~ 直子とレイコさんの部屋
ときどき私がジャズ・ピアノの真似事して教えてあげたりしてね。こういうのがバド・パウエル、こういうのがセロニアス・モンクなんてね。
下巻 P13 ~ レイコさんの回想
ドイツ語の授業が終わると我々はバスに乗って新宿の町に出て、紀伊国屋の裏手の地下にあるDUGに入ってウォッカ・トニックをを二杯ずつ飲んだ。
下巻 P42 ~ 緑と昼間から酒を飲む
おかわりが来るまで緑はカウンターに頬杖をついていた。僕は黙ってセロニアス・モンクの弾く「ハニサックル・ローズ」を聴いていた。
下巻 P47 ~ 緑と昼間から酒を飲む
それでみんな同じような本を読んで、みんな同じような言葉ふりまわして、ジョン・コルトレーン聴いたりパゾリーニの映画見たりして感動してるのよ。そういうのが革命なの?
下巻 P62 ~ 緑が大学の連中のインチキさを語る
僕は通勤電車みたいに混みあった紀伊国屋書店でフォークナーの「八月の光」を買い、なるべく音の大きそうなジャズ喫茶に入ってオーネット・コールマンだのバド・パウエルだののレコードを聴きながら熱くて濃くてまずいコーヒーを飲み、買ったばかりの本を読んだ。
下巻 P96 ~ 孤独な日曜日
大きなカップでコーヒーを飲み、マイルス・デイヴィスの古いレコードを聴きながら、長い手紙を書いた。窓の外には細い雨が降っていて、部屋の中は水族館みたいにひやりとしていた。
下巻 P129 ~ 日曜日、直子への手紙を書きながら
雨の日曜日は僕を少し混乱させます。 ~途中省略~ 机の前に座って「カインド・オブ・ブルー」をオート・リピートで何度も聴きながら雨の中庭の風景をぼんやりと眺めているくらいしかやることがないのです。
下巻 P132 ~ 直子への手紙
シェーカーが振られたり、グラスが触れあったり、製氷機の氷をすくうゴソゴソという音がしたりするうしろでサラ・ヴォーンが古いラブ・ソングを唄っていた。
下巻 P132 ~ 緑とDUGで飲む
その時代にはジョン・コルトレーンやら誰やら彼やら、いろんな人が死んだ。人々は変革を叫び、変革はすぐそこの角までやってきているように見えた。
下巻 P162 ~ 1969年
具体的な記述は少ないですが、ジャズの登場回数はかなり多めです。
直子はビル・エヴァンスのワルツ・フォー・デビイが好きだったみたいです。セロニアス・モンクもこの小説ではじめて登場します。
雨の日曜日にカインド・オブ・ブルーをオートリピートで聴くワタナベくん。彼の孤独を強く感じさせるシーンです。
あとはコルトレーンが学生運動の象徴というか、うさんくさい連中の象徴のような描き方をされてますね。やはり村上さん、コルトレーンのことがあまり好きではないんでしょう。
ダンス・ダンス・ダンス

五階建てのビルの地下にあるこぢんまりとしたバーで、ドアを開けると程よい音量でジェリー・マリガンの古いレコードがかかっていた。マリガンがまだクルー・カットで、ボタンダウン・シャツを着てチェット・ベイカーとかボブ・ブルクマイヤーが入っていた頃のバンド。昔よく聴いた。
僕はカウンターに座って、ジェリー・マリガンの品の良いソロを聴きながら、J&Bの水割りを時間をかけてゆっくりと飲んだ。八時四十五分をまわっても彼女は現れなかったが、僕は別に気にしなかった。上巻 P83 ~ ユミヨシさんと待ち合わせをしたバー
彼はB&Oのプレイヤーにレコードを乗せて、針を降ろした。スピーカーは懐かしいJBLのP88だった。JBLが神経症的なスタディオ・モニターを世界にばらまく前の時代、まだスピーカーがまともな音で鳴っていた時代の素敵な製品だった。彼のかけたのはボブ・クーパーの古いLPだった。「何がいい?何が飲みたい?」と彼が訊いた。
そして僕らはクールで清潔なウェスト・コースト・ジャズを聴きながらレモンをきかせたウォッカ・トニックを飲んだ。上巻 P271 ~ 五反田くんの生活感のない家
風呂を出ると僕はカリフラワーを茹で、それを食べながらビールを飲み、アーサー・プライソックがカウント・ベイシー・オーケストラをバックに唄うレコードを聴いた。無反省にゴージャスなレコード。十六年前に買った。一九六七年。十六年間聴いている。飽きない。
上巻 P337 ~ 猟師と文学によるキツい取調べから開放されて
都市の騒音さえもがアート・ファーマーのフリューゲル・ホーンみたいに優しく聞こえた。世界は美しく、腹も減っていた。
上巻 P338 ~ 猟師と文学によるキツい取調べから開放されて
僕はためしにジョン・コルトレーンの「バラード」のテープをかけてみたが、彼女はとくに文句は言わなかった。何が鳴っているのか気づきもしないようだった。僕はコルトレーンのソロにあわせて小さな声でハミングしながら車を走らせた。
下巻 P14 ~ 口をきかなくなったユキと車を走らせながら
そしてフレディー・ハバードの「レッド・クレイ」をハミングしながら家に帰った。
下巻 P15 ~ ユキはさよならも言わず行ってしまった
僕はジャズのFM局にラジオをあわせ、コールマン・ホーキンズだのリー・モーガンだのを聴きながら空港までのんびりと運転した。
僕は頭を空っぽにして運転に神経を集中し、「スタッフィー」や「サイドワインダー」にあわせて口笛と隙間風の中間くらいの音色の口笛を吹いた。下巻 P151 ~ ハワイの空港に向かう道中
五反田君はビデオ・デッキのスイッチを切り、新しい酒を作り、ビル・エヴァンスのレコードをかけた。
下巻 P230 ~ 五反田君の家
ジャズは結構たくさん出てきます。村上さんのジェリー・マリガンへの愛が、語り口に現れています。
ぼくはこの作品での主人公とユキの会話が好きです。ディック・ノースが死んだとき、彼にひどいことをしたと後悔するユキに対して、「ある種の物事というのは口に出してはいけないんだ」と諭すシーン、とても印象に残っています。五反田君が死んだあと「好きだったよ」と声を詰まらせるシーンは泣けます。
フレディー・ハバードのレッド・クレイは聴いたことないなあ。1970年代のハバード。今度聴いてみようかな。
国境の南、太陽の西
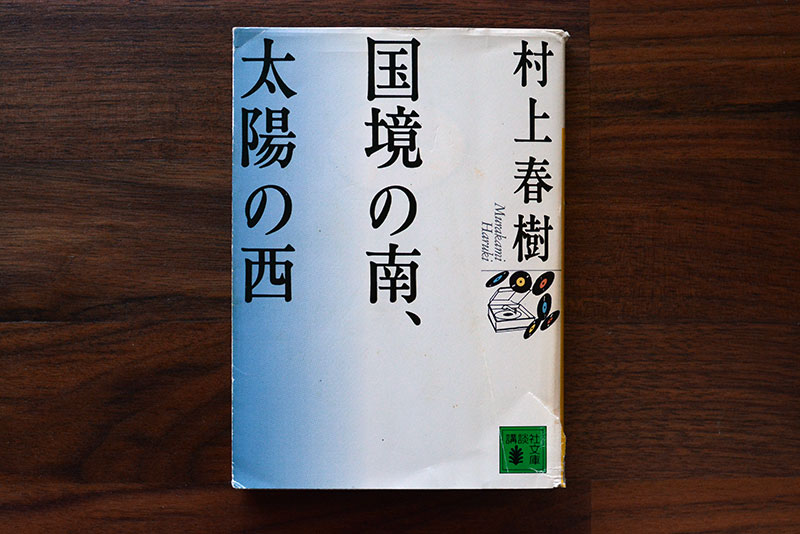
レコードはミステリアスなまでにずっしりと重く、分厚かった。クラシック音楽の他に、島本さんの家のレコード棚にはナット・キング・コールとビング・クロスビーのレコードが混じっていた。僕らはその二枚のレコードも本当によく聴いた。
P17 ~ 小学生の時の思い出
ナット・キング・コールが「国境の南」を歌っているのが遠くの方から聞こえた。もちろんナット・キング・コールはメキシコについて歌っていたのだ。でもその当時、僕にはそんなことはわからなかった。
P22 ~ 小学生の時の思い出
ピアノ・トリオが「コルコヴァド」の演奏を終えて、客がぱらぱらと拍手をした。いつもそうなのだが、真夜中に近くなると演奏はだんだんうちとけてきて、親密なものになっていった。
P122 ~ ハジメくんが経営するジャズバーにて
ピアノ・トリオがオリジナルのブルースの演奏を終えて、ピアノが「スタークロスト・ラヴァーズ」のイントロを弾き始めた。僕が店にいるとそのピアニストはよくそのバラードを弾いてくれた。僕がその曲を好きなことを知っていたからだ。
学生時代にも教科書出版社に勤めていた頃にも、夜になるとデューク・エリントンのLP「サッチ・スウィート・サンダー」に入っている「スタークロスト・ラヴァーズ」のトラックを何度も何度も繰り返して聴いたものだった。そこではジョニー・ホッジスがセンシティヴで品の良いソロを取っていた。その気だるく美しいメロディーを聴いていると、当時のことがいつもいつも僕の頭によみがえってきた。P131 ~ 島本さんとの再会
「最近のジャズ・ミュージシャンはみんな礼儀正しくなったんだ」と僕は島本さんに説明した。「僕が学生の頃はこんなじゃなかった。ジャズ・ミュージシャンといえば、みんなクスリをやっていて、半分くらいが性格破綻者だった。でもときどきひっくりかえるくらい凄い演奏が聴けた。僕はいつも新宿のジャズ・クラブに通ってジャズを聴いていた。そのひっくりかえるような経験を求めてだよ」
P148 ~ ハジメくんジャズ・ミュージシャンについて語る
僕はベーシストが「エンブレサブル・ユー」の長いソロを続けているのに耳を澄ましていた。ピアニストが時折コードを小さく叩き、ドラマーは汗を拭いて、酒を一口飲んでいた。
P149 ~ ハジメくんのお店で演奏するピアノ・トリオ
ピアノ・トリオがいつものように「スタークロスト・ラヴァーズ」の演奏を始めた。
「素敵な曲ね」僕は頷いた。「とても綺麗な曲だ。でもそれだけじゃない。複雑な曲でもある。何度も聴いているとそれがよくわかる。簡単に誰にでも演奏できる曲じゃない」と僕は言った。「『スタークロスト・ラヴァーズ』、デューク・エリントンとビリー・ストレイホーンがずっと昔に作った。一九五七年だったっけな」P232 ~ ハジメくんスタークロスト・ラヴァーズについて語る
おそらく村上作品の中で、一番ジャズが出てくる小説がこれです。上記以外にも、実はジャズに関する記述は出てきます。けれどそのほとんどが、ナット・キング・コールについてなので、ここでは一部を除いて割愛しました。
主人公のハジメくんはジャズバーを経営している設定で、これはまさに村上春樹さん自身の経験をもとに書いていると思われます。お店の設定はずいぶん違ってそうですが。
ハジメくんが通った新宿のジャズ・クラブは「新宿ピット・イン」のことかな?ぼくも東京に行ったとき、新宿ピットインでジャズライブを聴きました。また行きたいな。
ハジメくんのお店のピアノトリオが演奏していた「コルコヴァド」は、ぼくも好きなオスカー・ピーターソンの「WE GET REQUESTS」のA面1曲目で聴くことができます。とても良い曲です。
村上春樹さんのジャズ本「ポートレイト・イン・ジャズ」の中で、実はナット・キング・コールは「国境の南」を歌っていなかった・・・という事実が明かされています。村上さんの勘違いだったそうです。勘違いを題材にして、1冊の小説を書いてしまったんですね。
ねじまき鳥クロニクル

彼はおそらくイージーリスニング・ミュージックのマニアなのだ。アルバート・アイラーやドン・チェリーやセシル・テイラーの熱烈な信奉者が駅前の商店街のクリーニング屋の主人になるというようなことは果たしてあるのだろうか、と僕はふと思った。あるかもしれない。しかし彼らはあまり幸せなクリーニング屋にはなれないだろう。
第1部 P152 ~ クリーニング屋の主人についての考察
第3部 P92 ~ あちこちに観葉植物の鉢が置かれ、天井の真っ黒なボーズのスピーカーからはキース・ジャレットのいささかまわりくどいソロピアノが小さな音で流れていた。
とても長い小説なのに、ぜんぜんジャズが出てきません。ジャズが出てきそうな雰囲気すらありません。どうしたんだ村上さん?
ねじまき鳥クロニクルの主人公は、あまり音楽に興味がなさそうです。ファッションにも興味がなさそうだし、これまでの村上作品の主人公とはちょっと違います。
でもクリーニング屋で、アルバート・アイラーとかドン・チェリーのことを思い浮かべてるからなあ。音楽好きじゃない人がアルバート・アイラーのことを知ってるわけないし。うーん、そのへんの設定がよくわかりませんね。
村上春樹さんはキース・ジャレット嫌いで有名ですが、この小説の中でも「いささかまわりくどいソロピアノ」と、簡潔に批判しています。
海辺のカフカ

本を読むのに疲れると、ヘッドフォンのあるブースに座って音楽を聴いた。音楽についての知識はまったくなかったから、そこにあるものを右から順番にひとつひとつ聴いていった。僕はそのようにしてデューク・エリントンやビートルズやレッド・ツェッペリンの音楽に巡りあった。
上巻 P57 ~ カフカくん子供時代の図書館の思い出
それからポーチに座って森を眺め、ウォークマンで音楽を聴く。クリームを聴き、デューク・エリントンを聴く。
上巻 P232 ~ 大島さんの小屋で
それから納戸からもってきた古いレコードを順番にターンテーブルの上に載せる。ボブ・ディランの「ブロンド・オン・ブロンド」、ビートルズの「ホワイト・アルバム」、オーティス・レディング「ドック・オブ・ザ・ベイ」、スタン・ゲッツの「ゲッツ/ジルベルト」。どれも60年代後半に流行った音楽だ。
下巻 P38 ~ 甲村図書館の部屋で
それからポーチに座ってMDウォークマンでレイディオヘッドを聴く。僕は家を出てから、ほとんど同じ音楽ばかり繰り返し聴いている。レイディオヘッドの「キッドA」とプリンスの「グレーティスト・ヒッツ」、そしてときどきジョン・コルトレーンの「マイ・フェヴァリット・シングズ」。
下巻 P244 ~ 山の中で運動メニューをこなすカフカくん
僕は沈黙を埋めるために口笛を吹く。「マイ・フェヴァリット・シングズ」、ジョン・コルトレーンのソプラノ・サックス。もちろん僕のたよりない口笛では、びっしりと音符を敷きつめたその複雑なアドリブをたどることはできない。
下巻 P276 ~ 森の奥深くに足を踏み入れたカフカくん
いつのまにかジョン・コルトレーンはソプラノ・サックスのソロを吹きやめている。そして今ではマッコイ・タイナーのピアノ・ソロが、耳の奥で鳴り響いている。左手が刻む単調なリズムのパターンと、右手が積みかさねるぶ厚いダークなコード。それは、誰か(名前をもたない誰か、顔をもたない誰か)のうす暗い過去が、臓物みたいにずるずると暗闇の中からひきずりだされていく様子を細部までありありと、まるで神話の場面のように描写している。
下巻 P277 ~ 森の奥深くに足を踏み入れたカフカくん
僕は歩きつづける。ジョン・コルトレーンがまたソプラノ・サックスを手にとる。
下巻 P280 ~ 森の奥深くに足を踏み入れたカフカくん
耳の奥でジョン・コルトレーンはまだ迷宮的なソロをつづけている。そこには終わりというものがない。
下巻 P284 ~ 森の奥深くに足を踏み入れたカフカくん
海辺のカフカは、はじめて読んだ時あまり好きではなかったのに、数年後に読み返したら「こんなに面白かったっけ?」とビックリしました。
なんといっても、ナカタさんとホシノ青年のコンビが抜群にいい。これまでの村上ワールドにはいなかったタイプの2人が、本当に良い味を出してますよね。ジャズではなくクラシックですけど、ホシノ青年が大公トリオの演奏を好きになるくだりは、読んでいてほっこりします。
ジャズで言うと、コルトレーンの記述が印象的です。それと村上さん、本当にデューク・エリントンのことが好きなんだなあ。とてもよく登場しますから。
アフターダーク
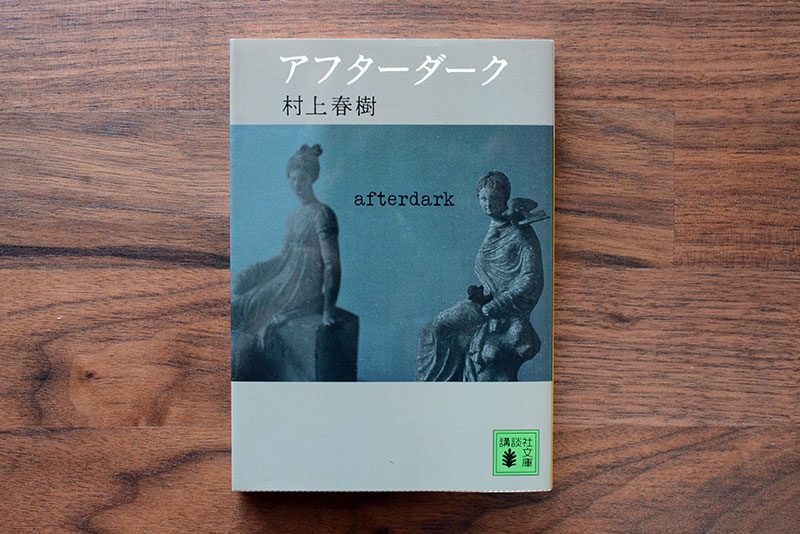
「中学生のときに、中古レコード屋で「ブルースエット」っていうジャズのレコードをたまたま買ったんだよ。古い古いLP。どうしてそんなもの買ったのかなあ。思い出せない。ジャズなんてそれまで聴いたこともなかったからさ。でもとにかく、A面の1曲めに「ファイブスポット・アフターダーク」っていう曲が入っていて、これがひしひしといいんだ。トロンボーンを吹いているのがカーティス・フラーだ。初めて聴いたとき、両方の目からうろこがぼろぼろ落ちるような気がしたね。そうだ、これが僕の楽器だって思った。僕とトロンボーン。運命の出会い」
男は「ファイブスポット・アフターダーク」の最初の八小節をハミングする。「知ってるよ、それ」とマリは言う。P32 ~ 高橋がトロンボーンを始めたきっかけ
でもだ、なんだか信じられないね。今どき「ファイブスポット・アフターダーク」を知ってる女の子がいるなんてな。まあいいや、とにかくそのカーティス・フラーにしびれまくって、それがきっかけでトロンボーンを始めることになった。
P33 ~ マリがその曲を知ってることに驚く男
二人は小さなバーのカウンターに腰掛けている。店にはほかに客はいない。ベン・ウェブスターの古いレコードがかかっている。「マイ・アイデアル」。1950年代の演奏だ。
P80 ~ カオルとマリ、バーにて
ボタンを押すと、針が盤面に降りる。かすかなスクラッチ・ノイズ。それからデューク・エリントンの「ソフィスティケイティッド・レイディー」が流れ出す。ハリー・カーネイの気怠いバス・クラリネット・ソロ。
P94 ~ カオルとマリ、バーにて
気怠く、官能的なエリントンの音楽。真夜中の音楽だ。
P97 ~ カオルとマリ、バーにて
高橋が「ファイブスポット・アフターダーク」のテーマを口笛で軽く吹きながら、牛乳を物色している。
P126 ~ コンビニ店内
電気ピアノとウッド・ベースとドラムズのトリオをバックに、高橋が長いトロンボーンのソロを吹いている。ソニー・ロリンズの「ソニームーン・フォア・トゥー」。それほど速くないテンポのブルース。悪くない演奏だ。
P253 ~ 高橋のバンド練習風景
ぼくは村上作品については、何度も何度も繰り返す読みますが、この「アフターダーク」と「スプートニクの恋人」に関しては、たぶん2回くらいしか読んでません。
カーティス・フラーの曲がタイトルになっているくらいだから、ジャズの登場回数も多めです。ソニー・ロリンズの名前は、村上作品ではじめて出てきたんじゃないでしょうか。
1Q84

バーに入ったのは七時少し過ぎだった。ピアノとギターの若いデュオが「スイート・ロレイン」を演奏していた。ナット・キング・コールの古いレコードのコピーだが、悪くない。
Book1 前編 P130 ~ 仕事を終えた青豆が入ったバー
彼女は本を読みながら、カティサークが運ばれてくるのを待った。そのあいだにブラウスのボタンをひとつさりげなく外した。バンドは「イッツ・オンリー・ア・ペーパームーン」を演奏していた。ピアニストがワンコーラスだけ歌った。
Book1 前編 P135 ~ 仕事を終えた青豆が入ったバー
しかし学校のクラスの中にディスレクシアの子供が一人か二人いたとしても、決して驚くべきことではない。アインシュタインもそうだったし、エジソンもチャーリー・ミンガスもそうだった。
Book1 前編 P232 ~ ふかえりが読字障害だと知って
しかし彼女はクラシック音楽よりは古いジャズのレコードが好きだった。それも古ければ古いほど良いみたいだった。その年代の女性にしてはいくぶん変わった趣味だ。とくに好きなのは、若い頃のルイ・アームストロングがW・C・ハンディーのブルーズを集めて歌ったレコードだった。バーニー・ビガードがクラリネットを吹き、トラミー・ヤングがトロンボーンを吹いている。
Book2 前編 P42 ~ 天吾の年上のガールフレンドのこと
「ルイのトランペットと歌ももちろん文句のつけようがなく見事だけど、私の意見を言わせてもらえるなら、ここであなたが心して聴かなくてはならないのは、なんといってもバーニー・ビガードのクラリネットなのよ」と彼女は言った。
とはいえ、そのレコードの中でバーニー・ビガードがソロをとる機会は少なかった。そしてどのソロもワン・コーラスだけの短いものだった。それはなんといってもルイ・アームストロングを主役にしたレコードだったから。しかし彼女はビガードの少ないソロのひとつひとつを慈しむように記憶しており、それにあわせていつも小さくハミングした。
バーニー・ビガードより優れたジャズ・クラリネット奏者はほかにもいるかもしれない。しかし彼のように温かく繊細な演奏のできるジャズ・クラリネット奏者は、どこを探してもいない、と彼女は言った。Book2 前編 P42 ~ 天吾の年上のガールフレンドが語る
「バーニー・ビガードは天才的な二塁手のように美しくプレイをする」と彼女はあるとき言った。「ソロも素敵だけど、彼の美質がもっともよくあらわれるのは人の裏にまわったときの演奏なの。すごくむずかしいことを、なんでもないことのようにやってのける。その真価は注意深いリスナーにしかわからない」
Book2 前編 P43 ~ 天吾の年上のガールフレンドがさらに語る
LPのB面六曲目の「アトランタ・ブルーズ」が始まるたびに、彼女はいつも天吾の身体のどこか一部を握り、ビガードが吹くその簡潔にして精妙なソロを絶賛した。そのソロはルイ・アームストロングの歌とソロとのあいだにはさまれていた。
Book2 前編 P44 ~ 天吾の年上のガールフレンドがさらに語る
「ほら、よく聴いて。まず最初に、小さな子供が発するような、はっとする長い叫び声があるの。驚きだか、喜びのほとばしりだか、幸福の訴えだか。それが愉しい吐息になって、美しい水路をくねりながら進んでいって、どこか端正な人知れない場所に、さらりと吸い込まれていくの。
ほらね。こんなわくわくさせられるソロは、彼以外の誰にも吹けない。ジミー・ヌーンも、シドニー・ベシエも、ピー・ウィーも、ベニー・グッドマンも、みんな優れたクラリネット奏者だけど、こういう精緻な美術工芸品みたいなことはまずできない」Book2 前編 P44 ~ 天吾の年上のガールフレンドがさらに語りまくる
ベッドの中で彼と一緒に聴くために、彼女が家から持参したLPレコードが数枚、レコード棚にあった。遥か昔のジャズのレコードばかりだ。ルイ・アームストロング、ビリー・ホリデイ(ここにもバーニー・ビガードがサイドマンとして参加している)、一九四〇年代のデューク・エリントン。どれもよく聴きこまれ、大事に扱われている。
Book2 前編 P168 ~ 天吾の年上のガールフレンドのレコード
あたりが薄暗くなってから部屋に帰ると、ふかえりは床に座って一人でレコードを聴いていた。年上のガールフレンドが残していった古いジャズのレコードだ。部屋の床にはデューク・エリントン、ベニー・グッドマン、ビリー・ホリデイといった人々のレコード・ジャケットが散らばっていた。
そのときターンテーブルの上で回転していたのは、ルイ・アームストロングの歌う「シャンテレ・バ」だった。印象的な歌だ。それを聴くと、天吾は年上のガールフレンドのことを思い出した。セックスとセックスとのあいだに二人はよくそのレコードを聴いた。その曲の最後の部分で、トロンボーンのトラミー・ヤングはすっかりホットになって、打ち合わせどおりにソロを終わらせることを忘れ、ラスト・コーラスを八小節ぶん余分に演奏してしまう。「ほら、ここのところ」と彼女は説明してくれた。Book2 後編 P113 ~ ふかえりレコードを聴く
これも好きな作品です。教団の話は面白いし、青豆がプロとしての仕事をするシーンも面白い。牛河さんの最期はとてもかわいそうです。殺す必用があったのかなあ。
結構ジャズは出てきますが、作品全体を通してジャズの匂いは希薄です。バーニー・ビガードへの村上さんの愛情がすごいです。
クラシック音楽の「シンフォニエッタ」がたびたび出てきて、それがきっかけでCDも売れました。そういう現象はジャズでは起こりませんよね。クラシックよりもジャズのほうが難解でマイナーな音楽ということでしょうか?
色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年

それから緑川は、「ラウンド・ミッドナイト」をためらいがちに弾き始めた。
P89 ~ 灰田の昔話
灰田青年はジャズにとくに知識があるわけではなかったが、セロニアス・モンクの作ったその曲はたまたま知っていたし、緑川の演奏は芯の通った見事なものだと感じた。
P90 ~ 灰田の昔話
緑川が灰田の前でピアノを弾いたのは、それが最初で最後になった。中学校の音楽室で「ラウンド・ミッドナイト」を十五分弾いてしまうと、それで彼のピアノに対する関心はすっかり失せてしまったようだった。
P92 ~ 灰田の昔話
村上さんの作品から、どんどんジャズの姿が消えつつあります。この作品もなかなか面白いんだけど、何故か繰り返し読もうという気にはなれないなあ。
騎士団長殺し

私はシェリル・クロウのCDをプレーヤーから取り出し、そのあとにMJQのアルバムを入れた。「ピラミッド」。そしてミルト・ジャクソンの心地よいブルーズのソロを聴きながら、高速道路をまっすぐ北に向かった。
第1部 P40 ~ ひたすら車で北へ向かいながら
私自身は古い時代のジャズを聴きながら料理をするのが好きだった。よくセロニアス・モンクの音楽を聴いたものだ。「モンクス・ミュージック」が私のいちばん好きなセロニアス・モンクのアルバムだ。コールマン・ホーキンズとジョン・コルトレーンが参加して、素敵なソロを聴かせる。
第1部 P247 ~ 妻と暮らしていたときの思い出
セロニアス・モンクのあの独特の不思議なメロディーと和音を聴きながら、昼下がりにトマトソースをつくっていたのは、ほんの少し前のことなのだが(妻との生活を解消してからまだ半年しか経ってない)、なんだかずいぶん昔に起こった出来事のように思えた。
第1部 P247 ~ 妻と暮らしていたときの思い出
セロニアス・モンクを見てごらん。セロニアス・モンクはあの不可思議な和音を、理屈や論理で考え出したわけじゃあらない。彼はただしっかり目を見開いて、それを意識の暗闇の中から両手ですくい上げただけなのだ。
第1部 P361 ~ 騎士団長がセロニアス・モンクについて語る
古いスピーカーから古い時代のジャズが流れている。ビリー・ホリデーとかクリフォード・ブラウンとか。
第2部 P221 ~ 初老の店主が一人で切り盛りしている路地裏の喫茶店
この作品は完全にグレート・ギャツビーですよね。そして村上ワールド全開。これまでに出てきた要素がテンコ盛りです。ぼくは楽しく読めました。
ジャズはあまり出てきませんが、セロニアス・モンクのことが結構出てくるので、ぼくとしてはそれがうれしかったです。「モンクス・ミュージック」は実はレコードを持っていないので、いつか手に入れて聴きたいです。